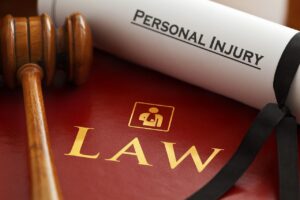少年事件における被害者の存在と被害者に対する配慮
1 少年事件における被害者
少年事件の中には、当然、被害者がいる事件もあります。
少年法の目的は、少年の健全育成を図る点にあります。
そのため、被害者の権利利益を保護するという観点は、成人の刑事手続以上になじみにくいという考え方もありました。
もっとも、少年法は、被害者に対し配慮する規定を置いており、解釈や運用による工夫もなされています。
更に、法改正により被害者の権利保護を目的とする規定が新設されるに至っています。
少年事件の対応にあたっては、被害者に対して十分に配慮した上で、対応することが望ましいと言えるでしょう。
2 被害者への情報提供
⑴ 少年審判規則7条1項に基づく記録の閲覧謄写
少年審判が非公開とされている趣旨から、原則として閲覧は認められず、家庭裁判所が許可した場合に例外的に閲覧・謄写が可能とされています。
運用上は、民事上の損害賠償請求権を行使するために必要という理由の場合に、法律記録の一部について許可されるものであったようです。
⑵ 少年法5条の2に基づく記録の閲覧謄写
意義
少年審判規則7条1項は一般的な規定であり、その後、少年法5条の2に基づく閲覧謄写の規定が新設されました(ただし、相当でない場合には認められません。)。
少年審判規則7条1項に基づく閲覧謄写が民事上の損害賠償請求権行使のために必要という理由で許可されていた運用であったのに対し、本条文に基づく閲覧謄写は、原則記録の閲覧謄写が認められる条文の立て付けとなり、事件を知りたいといった被害者心情面を理由としても認められることがあります。
また、いわゆる社会記録の閲覧謄写は認められていません。
申出の時期
本条に基づく閲覧又は謄写の申出は、審判開始決定後(少年法21条)から終局決定が確定した後3年が経過するまでの間です(少年法5条の2Ⅱ)。
そのため、審判不開始となった事件や、終局決定確定後3年を経過した事件については、少年審判規則7条1項の規定に基づいて閲覧又は謄写の許可が検討されます。
なお、この規定は、抗告審にも適用されると考えられています。
守秘義務等
本条に基づいて記録の閲覧や謄写をした場合には守秘義務等が課されます(少年法5条の2Ⅲ)。
⑶ 捜査機関による通知
警察では「被害者連絡制度」、検察庁では「被害者等通知制度」が整備されています(成人事件のみならず、少年事件も対象とされています。)。
警察の「被害者連絡制度」は、実施要領が定められています。
一定の事件の被害者や遺族に対し、検挙状況、人定事項、処分状況等についての連絡がなされるとされています。
検察庁の「被害者等通知制度」も実施要領が定められています。少年名(保護者の名前にとどまることもあります。)、罪名、事件番号、処分日、処分結果(多くの場合は送致された家庭裁判所名が記載されることになります。)等の連絡がなされるとされています。
⑷ 家庭裁判所による審判状況の説明
被害者等から申出があった場合に、家庭裁判所が審判期日における審判の状況を説明するという制度があります(少年法22条の6。但し、虞犯少年に係る事件は含まれません。)。
少年法31条の2Ⅰに基づく、審判結果等の通知は結果等が通知されるだけで、必ずしも十分な情報が提供されるとは限りません。
事件記録を謄写閲覧するには時間と費用が掛かりますので、これらのオプションとして活用が考えられます。
審判の傍聴とは異なり、対象事件に限定がないというのが一つの特色です。
なお、審判不開始決定がされた事件では、審判が開かれていないので、説明自体が実施されないようですので留意が必要です。
申出も終局決定確定後3年以内とされています(少年法22条の6Ⅱ)。
説明を受けた者には守秘義務等が課されます(少年法22条の6Ⅲ・同5条の2Ⅲ)。
抗告審への準用は認められないと考えられています。
⑸ 審判結果の通知
少年保護事件(虞犯事件は含まれません。)について終局決定をした場合において、被害者等から申出があった場合には、➀少年及びその法定代理人の氏名及び住居(法定代理人が法人である場合においては、その名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地)②決定の年月日、主文及び理由の要旨が通知されます(少年法31条の2Ⅰ。但し、相当でないものについては通知されないことがあります。)。
申出は、少年に対する決定が確定した後3年を経過した後はすることができません(少年法31条の2Ⅱ)。
通知を受けた被害者は、通知によって知り得た情報について守秘義務が課されます(少年法31条の2Ⅲ・5条の2Ⅲ)。
抗告審への準用は認められないと考えられていますが、裁量による実施は否定されていないようです。
3 被害者の少年保護手続への関与
⑴ 被害者からの意見聴取
実務上、家庭裁判所による社会調査の一環として、被害者に対する調査が行われる場合があります。
この目的は、あくまでも少年に対する処分の決定を行うための情報収集であり、被害者の意見が処分決定に直接反映されるものではないとされています。
もっとも、間接的に、被害者の心情を述べる機会が与えられることになると評価することは可能でしょう。
調査方法は、家庭裁判所の判断に依りますが、面接調査と書面による照会があります。
⑵ 意見聴取
被害者等から、「被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出」があるときに被害者が意見陳述する機会が認められています(少年法9条の2。但し、相当ではないときは認められません。虞犯少年に関する事件は対象外です。)。
抗告審への準用は認められないと考えられていますが、裁量による実施は否定されていないようです。
意見聴取の方法等
意見聴取の時期については特に定めがありません。
方法としては、審判の場で裁判官に対して行う、審判以外の場で裁判官又は調査官に行うといった方法があります。
口頭による意見陳述が原則とされていますが、意見を記載した書面提出による方法も可能とされています。
また、この意見陳述は、審判において少年を前にして行うことは保障されていません。
意見聴取の結果
家庭裁判所は、聴取した結果を、少年に対する処分決定のための一資料とすることができます。
なお、この聴取結果を非行事実の認定に用いることができるかについて、規定はおかれておらず、解釈に委ねられていますが、反対尋問権が保証されてないこと等の理由から消極的な見解が多数と考えられます。
意見聴取の内容等を知る方法
少年法9条の2に基づく意見聴取がされたときは、付添人(弁護士)に通知されます(少年審判規則13条の5)。
審判で聴取された場合には要旨が調書に記載され記録されます(少年審判規則33条Ⅱ④の2)。
審判期日外で意見聴取をした場合には、意見の要旨の作成が義務付けられ(少年審判規則13条の6Ⅰ・Ⅱ)、付添人等は閲覧等をすることができます。
被害者の意見は、少年の事件に対する理解を深めること等につながることも期待されますから、付添人としては意見聴取の内容を十分に把握する必要があるでしょう。
意見聴取が少年の在籍しない場で行われた場合には、裁判官や調査官からその要旨を適宜の方法で伝えるという運用も行われています。
⑶ 少年審判の傍聴
傍聴制度
被害者等から申出があった場合で、「少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当」と認められる場合に傍聴が認められる制度があります(少年法22条の4Ⅰ)。
被害者の傍聴については、少年審判規則29条により認めれば足りるという見解もありましたが、規則が定める「少年の親族、教員その他相当と認める者」とは少年の権利保護や審判の教育的機能に資する者と考えられ、被害者の権利利益を目的とする規定と読み込むのは難しいということもあり、被害者の権利利益の保護を目的とする規定として、少年審判の傍聴制度が新設されることになりました。
対象事件の限定
もっとも、対象となる事件は、故意の犯罪行為により被害者が亡くなった又は傷害を負った事件、刑法211条が定める業務上過失致死傷等の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪に限定されています(少年法22条の4Ⅰ➀~③)。
さらに、傷害を負った場合については「これにより生命に重大な危険を生じさせたとき」に限られるとされています。
また、12歳未満の少年に係る事件は、傍聴の対象から一律に除外されています。
虞犯事件も含まれません。
抗告審・再抗告審
抗告審(家庭裁判所の保護処分に対しなされた不服申立の当否を判断する裁判)の事件は対象外という考えが多数説です。
もっとも、少年事件では、抗告審が原審である家庭裁判所の判断を取り消す際に自判は認められていませんので、差し戻すか他の家庭裁判所の移送ということになります(少年法33条Ⅱ)。
そのため、再度行われる家庭裁判所での審判を傍聴できる可能性が生じます。
再抗告審は法律審であり、傍聴は認められないと考えられています。
付添人への意見聴取
傍聴制度は少年審判非公開の原則の例外であり、弁護士である付添人の意見を聞かなければならないとされています(少年法22条の5Ⅰ)。
付添人が選任されていない場合は、少年及び被疑者が不要とする意思を表示した場合を除いて、家庭裁判所が付添人を選任しなければならないとされています(少年法22条の5Ⅱ・Ⅲ)。
傍聴時の付添
被害者等が審判を傍聴する場合には、一定の者を付き添わせることができるとされています(少年法22条の4Ⅲ)。
守秘義務
少年法5条の2に基づく記録閲覧謄写と同様、傍聴者には守秘義務等が課されます(少年法22条の5・同5条の2Ⅲ)。
⑷ 証人尋問における保護
刑事手続の証人尋問においては、証人への付き添い(刑事訴訟法157条の4)、証人の遮蔽(刑事訴訟法157条の5)、ビデオリンク方式による証人尋問(刑事訴訟法157条の6)といった制度が導入されています。
これらの規定は、少年保護手続にも準用されますので(少年法14条2項)、少年審判において、被害者が証人として出廷される場合には利用が検討されることになります。
4. 被害者への対応の重要性
かつては処遇選択において、被害者の被害感情を考慮することは相当ではなく、弁償行為があれば要保護性の中で取り上げれば足りるという見解もあったようです。
もっとも、被害者からの意見聴取等の精度が導入され、聴取結果が処分決定のための資料にすることができると解されていることからすれば、処遇選択上被害者の意思は考慮されると考えられます。
また、被害者が事件記録の閲覧謄写や傍聴により、事件の真相を知りたいといった心情を持っていることも多分にあると思います。
少年事件においては、そうした被害者の立場や心情に配慮した上で、少年の健全育成を図るということが大切です。