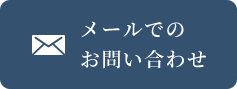「因果関係」とは?―相当因果関係説・危険の現実化と裁判実務
刑法上の犯罪の多くは、行為と結果の間に「因果関係」が存在することが成立の前提となります。
たとえば、人の死亡や傷害といった結果が生じた場合、その原因が被告人とされた人の行為によるものといえるかどうかは、罪の成否を分ける決定的なポイントになります。
しかし、どのような場合に因果関係が認められるかは一見して明確ではありません。
本記事では、刑事弁護の実務において重要となる因果関係の考え方について、条件説・相当因果関係説・客観的帰属論などの学説や、危険の現実化をはじめとする近時の判例動向を整理し、弁護の視点から解説します。
※ 因果関係については、学説・判例・裁判例の評価など様々な理解があり得ますが、本記事は、一般的な考え方や運用等をご紹介するもので、全てに賛同するわけではありません。
※ また、公開日の情報を基に作成しています。
1 因果関係とは
(1) 刑法上の意義
- 刑法における因果関係とは、構成要件に該当する実行行為と、それによって生じた構成要件的結果との間に必要とされる、一定の原因と結果の関係を指します。
- 結果犯(殺人罪、傷害致死罪、業務上過失致死傷罪など)が成立するためには、この因果関係の存在が必須とされています。
- 因果関係が認められなければ、その行為者に対して既遂犯(犯罪を完全に遂げた者)としての責任を問うことはできません。
- 未遂犯の処罰規定がある犯罪であれば未遂罪の成立が問題となります
- 未遂犯の処罰がない犯罪については不可罰となります。
- ポイント
- 刑法上の因果関係は、自然科学的な原因・結果の関係と同一ではありません。
- 行為者がその結果について刑法上の責任を負うのが妥当かどうかという、規範的な評価の側面が強い概念です。
(2) 条文上の根拠
刑法典には因果関係そのものを定義する条文はありませんが、例えば、人の死亡という結果が構成要件となっている、刑法第199条(殺人)刑法第204条(傷害)では、構成要件要素として求められることになります。
2 因果関係をめぐる学説の議論
(1) 条件説と相当因果関係説
因果関係の判断基準については、古くから様々な学説が対立してきました。
| 学説名 | 概要 | 判断基準 |
| 条件説 | 行為がなければ結果が発生しなかったという「条件関係」があれば、因果関係を認める。 | 「あれなければ、これなし」という事実的因果関係に尽きるとする。 |
| 相当因果関係説 | 条件関係がある事実のうち、一般人の社会生活上の経験に照らして、その行為からその結果が発生することが「相当」と認められる場合に、刑法上の因果関係を認める。 | 結果に対する予見可能性や蓋然性といった規範的評価を取り込む。 |
(2) 相当因果関係説における議論
- 相当因果関係説は、実行行為から結果が発生することが社会通念上、相当と評価できる場合に、刑法上の因果関係を認めます。
- ここでいう「相当」とは、「結果が発生することが一般的に予見可能といえること」すなわち「経験則上の通常性」が要求されることを意味するとされています。
- 最も重要かつ困難なのが、相当性を判断する際に基礎とする情報・資料である「判断基底」をどこまで含めるかという問題です。
- 「判断基底」(相当性を判断する基礎となる事情)をめぐり、主に以下のような対立がありました。
※ その他にも様々な議論がありますが、詳細は割愛します。
ア 客観的相当因果関係説
- 行為時に客観的に存在した事情と、一般人にとって予見可能な行為後の事情を基礎とする。
イ 折衷的相当因果関係説
- 行為時に一般人が認識・予見可能であった事情と、行為者が特に認識・予見していた事情を基礎とする。
(3) 近時の議論の潮流
ア 相当因果関係説の問題点
- 相当因果関係説では「判断基底」の範囲設定が曖昧であるため、事案の解決の際に予測可能性が難しい・不都合な結論になり得るなどの批判に晒されてきました。
- 特に介在事情(行為と結果の間に第三者の行為や被害者自身の特異な体質などが介入する事態)が存在する事案で、この問題が顕著になります。
- 当該行為が結果を発生させることが経験則上通常であるかが問われすが、行為と結果の間に異常な介在事情があった場合、その異常性が因果を断ち切ったと評価され、因果関係が否定される可能性もあります。
- 米兵ひき逃げ事件(最決 昭42・10・24 刑集21巻8号1116頁)や、大阪南港事件(最決平成2・11・20刑集44巻8号837頁)は、相当因果関係説において、専ら介在事情に対する予見可能性によって因果関係の有無を判断した場合の問題点が顕在化した事案ともいえます。
イ 客観的帰属論
- 近年、相当因果関係説の曖昧さを批判し、客観的帰属論が示されています。
- 行為が結果発生の危険性を創出したか、そしてその危険性が具体的な結果として現実化したかどうか、(危険の現実化)という規範的な判断枠組みに基づきます。
- この立場の特徴は、事実的因果関係と法的因果関係とで区別し、法的因果関係の判断基底の資料を限定しない点に特徴があるとされています。
- また、行為の危険が現実化したかを検討するにあたり、2つの類型に大別されると言われています。
- 当該結果を発生させる危険性が実行行為に存在しその危険が結果を実現したかという直接型
- 実行行為には結果を発生させる危険性はないが、実行行為の危険が介在事情を通して間接的に実現したと言えるかという間接型
3 裁判例・判例の動向|危険の現実化
(1) 傾向
- 最高裁判所は、特定の学説の立場を明示することは必ずしもありませんが、近年、判例・裁判例において、「行為の危険性の現実化」を意識した判断枠組みが示されています。
- これは、行為が創出した危険が、介在事情(行為の後に発生した特殊な事情)を伴いながらも、最終的に結果として現れたと評価できるか、という点を重視するものといえます。
(2) 因果関係が肯定された著名な裁判例
最高裁判例では、行為と結果の間に被害者や第三者の行為が介在した場合でも、その介在事情が実行行為によって「誘発」されたり、「利用」されたりした場合、因果関係を認める傾向があります。
| 裁判情報 | 事案概要 | 判旨(因果関係肯定) | 類型 |
|---|---|---|---|
| 高速道路逃走事件 (最決平15・7・16) |
激しい暴行を受けた被害者が、極度の恐怖から逃走を図り、高速道路に進入して車に轢かれ死亡した。 | 被害者の行動は、暴行から逃れる方法として「著しく不自然、不相当であったとはいえない」。暴行に起因するものと評価できる。 | 間接型|暴行が逃走という介在事情を誘発した。 |
| 監禁致死事件 (最決平18・3・27) |
被告人が被害者を自動車のトランクに監禁し路上に停車したところ、第三者の甚だしい前方不注意による追突事故で被害者が死亡した。 | 判旨は明言しないが、監禁行為は、交通事故に巻き込まれるという重大な危険性を有していたことを前提にし、追突事故は特異な事態ではなく、因果関係を肯定したように考えられる。 | 間接型|監禁行為が、第三者の過失による事故という介在事情を利用して結果を招いたと解される。 |
| 大阪南港事件 (最決平2・11・20) |
被告人の暴行により、被害者が内因性高血圧性橋脳出血を発生し意識不明に陥った。その後、第三者の暴行が介在したが、死亡の直接原因は最初の暴行による出血であり、死期を幾分早めたに過ぎなかった。 | 犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、因果関係を肯定できる。 | 直接型|実行行為が致命的な傷害を形成しており、介在事情の寄与度が低い。 |
4 因果関係が否定された著名な裁判例
(1) 米兵ひき逃げ事件(最決昭42・10・24)
この最高裁判例(最決昭42・10・24 刑集21・8・1116)は、相当因果関係説における因果関係の判断基準、特に「因果経過の相当性」を否定した代表的な事例とされています。
- 事案の概要
- 被告人とされた人は、自転車に乗っていた被害者Bを車体屋根の上に跳ね上げたまま逃走を続行しました。
- 同乗していたAは、走行中に屋根の上のBに気づき、Bを逆さまに引きずり降ろした結果、Bはアスファルト舗装道路に転落して死亡しました。
- 被害者の死亡原因となった傷害が、当初の衝突によるものか、同乗者Aの引きずり降ろしによるものか確定しがたい状況でした。
- 判旨|相当因果関係説を意識?
- 最高裁は、被告人の過失行為と被害者の死亡との間の因果関係を否定しました。
- その理由として、同乗者Aが進行中の自動車の屋根の上から被害者を逆さまに引きずり降ろし、舗装道路に転落させるという行為は、「経験上、普通、予想しえるところではなく」、被告人の過失行為から被害者の死の結果が発生することが、「われわれの経験則上当然予想しえられるところであるとは到底いえない」と判断しました。
- 整理
- 相当因果関係説は、実行行為から結果が発生することが社会通念上「相当」と評価できる場合に法的因果関係を認める立場であり、「通常」で「結果が発生することが一般的に予見可能といえること」を求めます。
- 本件では、被告人の過失行為(ひき逃げ・救護義務違反)と死亡結果の間に、第三者による殺人にも類する異常な故意行為という介在事情が介入しました。
- 最高裁は、この介在事情の異常性(経験的非通常性)を重視し、因果経過が通常性・相当性を欠くものとして、因果関係を否定したと理解されています。
(2) 福岡高判平27・8・28(判例秘書)
この高裁判決は、実行行為(暴行)の危険性が介在事情を介して結果に現実化したか否かという、危険の現実化理論の枠組みに基づいて因果関係を否定した事例として注目されます。
- 事案の概要
- 被告人とされた人が被害者に暴行を加え、傷害を負わせました。
- これらの傷害自体は被害者を死に至らしめるほど重篤ではありませんでした。
- 暴行が終了した後、被告人とされた人は被害者を布団に運ぼうとした際、バランスを崩して床に落とし、さらに自分も覆いかぶさるように倒れ込みました。
- この最後の行為(介在事情)により、被害者は致命傷となる別の傷害を負い死亡しました。
- 被告人の最後の行為は、当初の暴行とは異なり、被害者を介助・回復させることを目的とした行動でした。
- 被告人とされた人が被害者に暴行を加え、傷害を負わせました。
- 判旨と危険の現実化理論の適用
- 福岡高裁は、最初の暴行行為と被害者の死亡結果との間の因果関係を否定しました。
- 因果関係が否定された理由は、致命傷を生じさせた最後の行為が、当初の暴行行為が終了し、被害者の介助を目的としてとられたものであり、「目的や性質を全く異にしている」点にあります。
- さらに、暴行行為の結果として被害者を抱きかかえて運ぶ行為に至ったものの、その後の「バランスを崩して体を落とし、その上に覆い被さるように倒れること」は、「暴行行為に引き続いて生ずるものとして、通常あり得べきものともいい難い」とされました。
- 結論として、被害者の死亡結果は、「被告人による暴行の危険が現実化したものとはいえず」、因果関係を認められない、と判示されました。
- 整理
- これは、実行行為(暴行)が有する危険性(身体を傷つける危険)が、介在事情(介助行為中の不測の転落・覆いかぶさり)を介して結果に間接的に現実化したとは評価できないという判断と言えます。
- 特に、介在事情が実行行為の危険性を孕んでいるとはいえず、異質な危険の現実化であったと判断されたものと言えます。
(3) 裁判例の比較
- 米兵ひき逃げ事件は、介在した第三者の行為が極めて異常(故意)であったため、その因果経過の「通常性」(予見可能性)の判断において否定されました(判旨からは、予見可能性を重視しているようにも見え、相当因果関係説と親和的に読めます。)。
- 一方、福岡高判は、介在した行為者自身の行為が、当初の犯罪行為(暴行)の文脈を完全に離れ、介助という異質な目的で行われた結果、その行為が作り出した新しい危険(転落)が結果を招いたと見なされました。
- 実行行為が有する危険が結果に結びついているか(危険の現実化)を重視する現代の因果関係判断の潮流を示しているともいえるかもしれません。
5 刑事弁護における因果関係の重要性
因果関係は、事実認定(行為がなければ結果が起こらなかったか)に留加え、行為者に結果を帰属させるべきかという規範的な判断(法律的因果関係)に深く関わります。
弁護活動においては、
因果関係を基礎づける事実がそもそも認められるか、証拠を検討し、主張立証していきます。
さらに、
事実的因果関係の欠如( そもそも、被告人の行為と結果との間に医学的、物理的な因果関係がないこと。)を主張立証すること
法的因果関係の切断(被告人とされた人の行為の後に介在した事情(被害者や第三者の異常な行動、医師の重過失など)が、実行行為の創出した危険とは無関係に、独立して結果を発生させたこと(危険の現実化の否定)を主張立証すること
が求められます。
特に、人が亡くなったなどの結果が重い犯罪については、重い刑罰が言い渡される可能性もあります。
この因果関係の有無を(特に医学等の専門家の助力を得ながら)専門的かつ多角的に検討することが不可欠です。
当事務所は、依頼者の防御権を最大限に守ります。
是非ご相談ください。