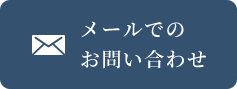過剰防衛とは?正当防衛との違いと行為の「一連一体」の最高裁判例
正当防衛を主張しても、「やりすぎ」と判断されて過剰防衛とされるケースは少なくありません。
過剰防衛は無罪にはなりませんが、刑の減軽や免除が認められる可能性がある、刑事弁護における重要な戦略です。
もっとも判例裁判実務では、複数の反撃行為を「一連の防衛行為」として評価できるか(防衛行為の一体性)について、判断され、正当防衛・過剰防衛の判断・成立範囲が厳格化しています。
本記事では、過剰防衛の基本的枠組みから、実務の分水嶺となった平成20年・21年の最高裁判例までを整理し、弁護士の視点から実務対応を解説します。
※ 正当防衛については様々な議論がありますが、本記事は、一般的な理解や代表的な見解をご紹介するもので、全てに賛同するわけではありません。
※ また、公開日の情報を基に作成しています。

1 過剰防衛の基本的枠組みと問題意識
(1) 刑法36条2項の規定
- 刑法36条2項は、「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」と規定しています。
- これは、急迫不正の侵害という緊急状況下で、防衛の意思を持って反撃したものの、その手段や態様が「やむを得ずにした行為」(相当性)の範囲を逸脱してしまった場合を指します。
- 「任意的減免」の法的性格 過剰防衛は、違法性が阻却される正当防衛とは異なり、「犯罪」自体は成立します。しかし、刑が減軽または免除される可能性がある「任意的減免事由」とされています。
(2) 実務上の問題意識:防衛か、攻撃か
- 過剰防衛が認められるためには、大前提として刑法36条1項の「急迫不正の侵害」と「防衛するため」(防衛の意思)の2要件を充足している必要があります。
- 実務上、過剰防衛となった場合に争点となりやすいのは、また反撃を継続する中で侵害が終了したにもかかわらず暴行を続けた場合(量的過剰)に、それを「一つの防衛行為の行き過ぎ」と見るか、それとも「侵害終了後の単なる攻撃(犯罪行為)」と見るかという点です。
2 過剰防衛の類型と学説の議論
(1) 刑の減免根拠に関する学説
なぜ過剰防衛は刑が減軽・免除されるのかについて、以下の3つの立場が対立しています。
ア 違法性減少説
正当な利益を保護しようとした側面があるため、通常の犯罪に比べて違法性が減少していると考える立場です。
イ 責任減少説
相手から攻撃を受けた緊急状態の下での恐怖、驚愕、興奮、狼狽といった心理的動揺により、適法行為に出る期待可能性が減少していることを重視する立場です。
ウ 二元説(通説・判例的立場)
違法性と責任の両面が減少していると考える立場です。
判例は明言はしていませんが、この考え方に親和的とされています。
(2) 質的過剰と量的過剰の区別
過剰防衛は、その逸脱の態様により、講学上2つの類型に整理されます。
ア 質的過剰(強度の過剰)
侵害が継続している間に、防衛手段として過度に(必要以上に)強力な対抗手段を用いる場合です。
- 具体例
- 素手で殴りかかってきた相手に対し、いきなりナイフで刺すようなケースがこれに当たります。
- 判断基準
- 防衛行為の「相当性」(武器対等の原則など)によって決せられます。
イ 量的過剰(時的な過剰)
当初は防衛の範囲内であったが、勢い余ってあるいは心理的な動揺等から反撃を継続するうちに防衛の程度を超えてしまう場合です。
一般的には、相手の侵害が止んだか否か質的過剰防衛と区別されます。
- 具体例
- 相手を倒して侵害が止まったのに、さらに追い打ちで殴り続けるようなケースです。
- 実務上の課題
- 侵害終了後の暴行は、客観的には「急迫性」を欠くため、これを「防衛行為」の一部として刑を減免すべきかどうかが激しく争われます。
3 防衛行為の一体性判断(一連の行為論)
(1) 分析的評価か、一体的評価か
過剰防衛、特に量的過剰が問題となる事案では、複数の反撃行為をどう評価するかがで結論が左右され得ます。
ア 分析的評価
侵害継続中の行為(正当防衛)と、侵害終了後の行為(単なる犯罪)に切り離して評価する手法です。この場合、後者の行為に刑の減免は適用されません。
イ 一体的評価
- 複数の行為を「一連の防衛行為」として包括的に評価する手法です。全体として過剰防衛となれば、後者の行為も含めて刑の減免の対象となります。
- 侵害終了後の反撃行為についても侵害終了前の反撃行為と合わせて全体として過剰防衛を認め得ることについては、勢い余って(ついやりすぎて)反撃をしてしまった場合に全て刑の減免の余地がないとすると酷であるという価値判断もあるように思います。
- 判例は一連の行為といえる場合には一体的評価をしているといえます。
(2) 一体的評価が採用される理由
- 常に分析的評価をするとなると、社会的には一つのエピソードとみることができる現象を人為的に分断しすぎることになり、不自然ではないかという点が指摘されています。
- また、常に分析的によるとなると、複数の暴行のうちいずれの暴行で重い結果が発生したか不明な場合には疑わしきは被告人の利益により、重い結果を処罰に反映できなくなるという点も指摘されています。
- なお、こうした立場に対しては、構成要件に該当する2つの行為を価値判断的に1つの行為と評価するところ、たとえば、単独で見れば適法であった行為を他の行為と合わせることによって、全体として違法と評価される場合もあり得る点に対し、疑問も呈されています。
- また、疑わしきは被告人の利益の原則により、重い結果を処罰に反映できなくなるという点も、正当防衛が成立しないことについて合理的な疑いがあるのであれば当然の結論であり、この原則を修正することについて疑問を呈する見解もあります。
(3) 一体性判断の基準
判例・実務では、以下の要素を総合考慮して一体性が判断されています。
ア 客観的関連性
時間的・場所的な近接性、および対抗手段の同一性があるかどうかを検討します。
イ 主観的関連性
第一の反撃から第二の反撃まで、一貫して「防衛の意思」が継続しているか、あるいは同一の意思決定に基づいているかが基準となります。
4 最決平成20年6月25日(刑集62巻6号1859頁)の解説
(1) 事案の概要
- 被告人は、Aから殴りかかられ、さらにアルミ製灰皿(直径19cm、高さ60cmの円柱形)を投げつけられたため、それを避けた反動で体勢を崩したAの顔面を右拳で殴打しました(第1暴行)。
- Aは後頭部を地面に打ち付けて仰向けに倒れ、意識を失って動かなくなりました。
- 被告人はその状況を認識しながら、「おれを甘く見ているな」と言い、倒れているAの腹部を足蹴にし、足で踏みつけるなどの暴行を加えました(第2暴行)。
- Aは第1暴行による頭部打撲で亡くなりました。
(2) 最高裁の判断(一体性の否定)
最高裁は、第1暴行と第2暴行を「別個の行為」と判断しました。
ア 侵害の終了と認識
第1暴行によりA転倒し動かなくなった時点で、更なる侵害行為に出る可能性はないことが客観的に明らかであり、被告人もそれを認識していたと認定しました。
また、専ら攻撃の意思に及んでいるのであるから、第2暴行が正当防衛の要件を満たさないとも判示しています。
イ 意思内容の変容
そして第1暴行と第2暴行は、時間的場所的に連続性しているものの、防衛の意思の有無で明らかに性質を異にし、被告人が発言(「おれを甘く見ているな」等)した上で抗拒不能な被害者に対して相当激しい態様の第2暴行に及んでいることにもかんがみると、その間には断絶があると判示しました。
ウ 結論
第1暴行と第2暴行の間には「断絶」があるため、一連の行為として過剰防衛の成立を認めるのは相当ではなく、第2暴行については単なる傷害罪(正当防衛も過剰防衛も成立しない)が成立するとしました。
(3) 判例の意義
- 本決定は、たとえ時間的・場所的に連続していても、侵害が終了したことの認識があり、かつ意思が報復・攻撃に転換した場合には、一体性が否定されるという「全体的評価の限界」を示しました。
- 第1暴行による亡くなったことが認定できた事案
- なお、本件では、第1暴行により被害者が亡くなったことは認定でき、第1暴行について正当防衛が成立する事案のようでした。
- 仮に第1暴行と第2暴行を一体として判断した場合には、傷害致死罪が成立し、過剰防衛が認められるという帰結になる事案でした(第1審の結論)。
- 行為を分断すると、最高裁のように、第1行為の傷害致死罪について正当防衛が成立し無罪、第2行為は傷害罪が成立するが正当防衛も過剰防衛も成立しないという結論になります(控訴審も同じ。)。
- 仮に第1暴行と第2暴行を一体として判断した場合には、傷害致死罪が成立し、過剰防衛が認められるという帰結になる事案でした(第1審の結論)。
- 被告人のみ上告の場合に重い傷害致死罪の認定に変更できるか
- この場合に、仮に上告審が第1審と同じように、第1暴行と第2暴行を一体として判断した場合には、(傷害罪と比較して罪名が不利益で、かつ、控訴審が第1暴行について無罪とした)傷害致死罪が成立する(ただし、過剰防衛)ことになりますが、被告人側のみが上告していた場合に、全体として傷害致死罪(ただし過剰防衛)という認定が許されるのか、という訴訟法上の問題(いわゆる攻撃防御対象論)もあるとされています。
- この点については、正当防衛も過剰防衛も成立しない傷害罪より、過剰防衛が成立する傷害致死罪であれば刑が減免される余地もあり、上告審が傷害致死罪(過剰防衛)を認定することは許容され得る、重い刑を科さない限り上告審が職権調査を及ぼす考えもあり得ると、判例解説にて担当調査官の意見が紹介されています。
- この場合に、仮に上告審が第1審と同じように、第1暴行と第2暴行を一体として判断した場合には、(傷害罪と比較して罪名が不利益で、かつ、控訴審が第1暴行について無罪とした)傷害致死罪が成立する(ただし、過剰防衛)ことになりますが、被告人側のみが上告していた場合に、全体として傷害致死罪(ただし過剰防衛)という認定が許されるのか、という訴訟法上の問題(いわゆる攻撃防御対象論)もあるとされています。
- なお、本件では、第1暴行により被害者が亡くなったことは認定でき、第1暴行について正当防衛が成立する事案のようでした。
5 最決平成21年2月24日(刑集63巻2号1頁)の解説
(1) 事案の概要
- 居室内で、同居者Dが被告人に向けて折り畳み机を押し倒してきたため、被告人は机を押し返しました(第1暴行)。
- Dは机に当たって転倒し、反撃や抵抗が困難な状態になりましたが、被告人は間髪入れずDの顔面を数回殴打しました(第2暴行)。
- これによりDは全治3週間の傷害を負いましたが、その怪我は第1暴行によるものでした。
(2) 第1審と控訴審の概要
- 第1審
- 第1審は、第2暴行の時点でDの急迫不正の侵害があったとは認められず、被告人の行為は専ら攻撃の意図で及んだと推認され防衛の意思を欠いているなどとしました。
- 結論として正当防衛の主張を排斥しました。
- 控訴審
- 控訴審は、Dの攻撃をそれなりの強度と評価し、第2暴行が無ければまもなく態勢を立て直して再度の攻撃に及ぶことも客観的に可能であったと認められるとし、Aの急迫不正の侵害が終了したとは認められないとしました。
- もっとも、第2暴行の時点で、防衛手段としての相当性を欠いているとしました。
- 第1暴行と第2暴行は一連一体の行為として、正当防衛か過剰防衛かは全体として判断するべきとしました。
(3) 最高裁の判断(一体性の肯定)
最高裁は、第1暴行と第2暴行を「一連一体の行為」と判断し、全体として過剰防衛の傷害罪が成立するとしました。
ア 行為の一体性
「急迫不正の侵害に対する一連一体のものであり、同一の防衛の意思に基づく1個の行為と認められるから、全体的に考察して1項の過剰防衛として傷害罪の成立を認めるのが相当」としました。
イ 「有利な情状」としての考慮
第1暴行によって傷害が生じた経緯は、量刑上の「有利な情状」として考慮すれば足りるとしました。
(4) 判例の意義
- 本決定は、事例判断ではあるものの、質的過剰防衛の事案であっても、防衛の意思が連続している場合には、行為は一連一体として考えるべきことを示しました。
- また、傷害結果が正当防衛の成立する第1暴行で生じた場合でも、行為が一連一体であれば、全体として過剰防衛の傷害罪が成立するということを示し、分断すれば「正当防衛的な行為」である第1暴行により傷害が生じた点は、量刑上考慮すれば足りるとしました。
- なお、行為を一連一体と評価した上で、仮に傷害結果が第1暴行か第2暴行のいずれで生じたものが明らかではない場合には、「疑わしきは被告人の利益に」の原則により、(正当防衛が成立する)第1暴行により傷害が生じたとされるべきであると、判例解説にて担当調査官の見解が紹介されています。
6 弁護士から見た課題と実務対応
(1) 一連一体について
ア 結論の検討
- 平成20年決定でも問題意識が示されているように、一連一体と評価された場合に全体として過剰防衛として評価されるのが有利なのか、分断して各行為について評価されるのが有利なのかは一概に言いづらい面があります。
- たとえば、第1暴行で重い傷害結果が生じたところ分断的評価をすれば正当防衛が成立する・第2暴行では傷害結果が生じていない場合、分断して評価すれば第1暴行は正当防衛による無罪・第2暴行による暴行罪が成立するにとどまります。
- もっとも、分断される場合には、防衛の意思の連続性が途切れている可能性もあり、第2暴行は一方的に暴行した点で犯情として消極的な評価を受け得ます。
- 他方、全体として防衛の意思に貫かれており、全体として過剰防衛と評価された方が有利な可能性もありうるように思います。
- たとえば、第1暴行で重い傷害結果が生じたところ分断的評価をすれば正当防衛が成立する・第2暴行では傷害結果が生じていない場合、分断して評価すれば第1暴行は正当防衛による無罪・第2暴行による暴行罪が成立するにとどまります。
- したがって、傷害等の結果が発生している事案では、まず結果がどの暴行によって生じたものなのか十分に検討する必要があります。
イ 時間的場所的接着性の検討
短時間の出来事であれば、社会通念上は一つのエピソード(社会的1個性)であり、人為的に分断して評価すべきではないと主張しやすいと言えます。
ウ 主観的要素(意思の連続性)の検討
- 平成20年・21年判例で、行為の一連一体の結論が分かれたポイントは、「意思の連続性」でした。
- 平成20年判例のように、反撃の最中に「やったぞ」「思い知れ」といった相手を屈服させるような言動を発することは、防衛意思の断絶と評価される可能性があります。
- 当時の状態において、どのような心理で反撃行為を行わざるを得なかったかを、客観的証拠も踏まえて(現場の状況、負傷の有無等)主張立証していくことが考えられます。
- たとえば、恐怖や驚愕、必死の思いで反撃を続けていた等
- 当時の状態において、どのような心理で反撃行為を行わざるを得なかったかを、客観的証拠も踏まえて(現場の状況、負傷の有無等)主張立証していくことが考えられます。
- 平成20年判例のように、反撃の最中に「やったぞ」「思い知れ」といった相手を屈服させるような言動を発することは、防衛意思の断絶と評価される可能性があります。
(2) 取調べの対応
- また、主観的要素がポイントになる以上、被告人とされた人の供述が重要な証拠となり得ます。
- そもそも取調べに応ずるべきなのか、応ずるとして話をするべきなのかも慎重に検討する必要があります。
(3) 裁判員裁判における戦略
- 正当防衛・過剰防衛が争点となる事案では、傷害致死や殺人など裁判員裁判となる事案も少なくありません。
- そして、裁判員にとって、量的過剰や一体性といった法律用語は極めて難解です。
- そのため、正当防衛が認められる趣旨にさかのぼり、わかりやすい言葉を用い、事実関係を丁寧にプレゼンテーションする能力も求められています。
7 まとめ
過剰防衛の成否は、刑の減免が認められるかどうかという点で、裁判の結論を大きく左右します。
もっとも、その概念は非常に複雑で、特に裁判員裁判となった事案では専門性が強く求められる分野といっても過言ではありません。
とりわけ、防衛行為を「一連一体」と評価できるか、あるいは分断されてしまうかは、事実認定・供述内容・方針によって結果が分かれ得ます。
過剰防衛が疑われる事案でお困りの際は、是非ご相談ください。