- 依頼者と共に戦う、
プロフェッショナルであること。

- 私たちは、あなたの生活を護ります。
あなたの会社を護ります。
人生いつ起こるか分からないトラブル。
それを未然に防ぐこと。
そして起こってしまったとしても
影響を最小限に留めること。
私たちに関わる全ての人が、
いつでも笑顔でいられるように。
法律の専門家として、
あなたと一緒に戦います。
新着情報
2020.03.17
2020.02.26
2019.12.04
2019.11.08
ブログ情報
2023.10.14
2024.04.23
2024.04.19
2024.04.18
2024.04.16
-
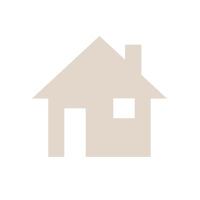
不動産
-
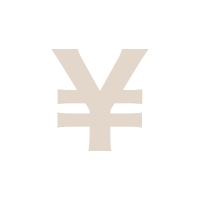
債権回収
-
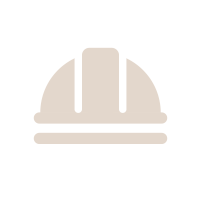
労働問題
-
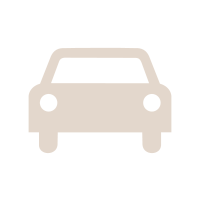
損害賠償(労災)
-
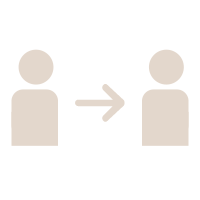
事業承継、相続
-
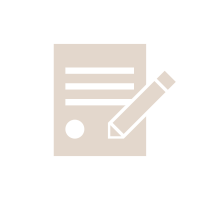
契約書
-

不当要求(クレーム)対応
-
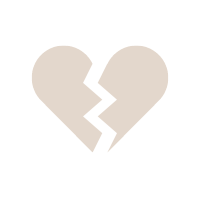
法的紛争
解決までの流れ
-
お問い合わせ
電話でお問い合わせ
03-3524-7281
受付時間 平日9:00〜18:00
メールでお問い合わせ
お問い合わせフォーム
チャットワークでお問い合わせ
Chatwork


-
相談・提案
来所又はZoomにて法律相談を行い、ご意向を尊重した解決方法を提案いたします。


-
契約
当事務所へご依頼いただける場合は、契約の手続きに入ります。
契約後は、ご提案した解決方法などに沿って各種交渉などを当事務所にて行います。