契約書を定める際に、契約の有効期間については忘れずに定めていると思います。
しかし、その規定の仕方次第では、思わぬところで足をすくわれかねません。
ここで契約書の期間について確認をしてみたいと思います。

1 契約の始まりと終わり 【期間の考え方】
⑴ はじめに
以下のような条項例をもとに、契約書の期間について、考えてみたいと思います。
【条項例1】
本契約の有効期間は、令和4年5月1日より同年8月31日までとする。
このような定め方は、一義的に理解することができ、一番誤解が生まれにくいです。
なお、西暦でも和暦でも、どちらでも大丈夫です。
【条項例2】
本契約の有効期間は、令和4年5月1日より3カ月間とする。
このように、日付ではなく、期間を定める方法もよく見られると思います。
この定め方は、有効期間の長さが分かりやすいメリットがあります。
ただし、期間の計算方法には注意をしましょう。以下で説明を加えていきます。

条項例2の場合、契約の終わりは、7月末日まででしょうか?
それとも、8月1日は含めるのでしょうか?

期間については、民法に規定があります。
ただ、これを読んでいるだけでは全然頭にも入りませんので、具体的に見ていきましょう。
民法第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
民法141条
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
民法142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
民法143条
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2項
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
⑵ 「日」単位で有効期間を定めた場合
【開始日】
原則として初日を参入しません(民法140条)。
ただし、初日の起算点が午前0時から始めるときは初日を参入します(同条ただし書)。
(具体例で考えてみよう)
本契約の締結日より10日間とする。
→ 「本契約の締結日」を「午前0時から始めるとき」と考えられるかどうかで、開始日が変わります!!
→ 契約の締結を「5月1日」のオフィスアワーに結んだと仮定します。
そうすると、初日を参入しないルールにより、契約は、翌日の5月2日からとなります。
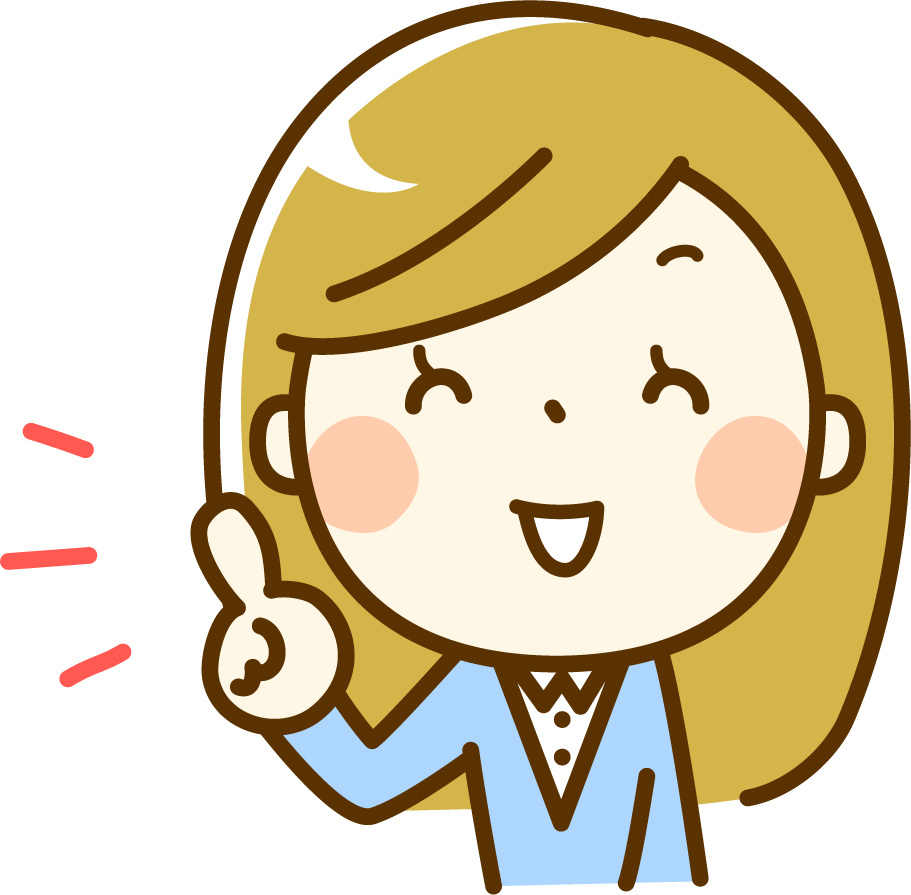
契約締結したその瞬間から、契約の有効期間が始めると思っていましたが、必ずしもそうではないのですね。
これは知りませんでした、、、思わぬ落とし穴ですね。
下手な誤解を生まないためには、日付を活用していくことも考えてみます。
ただし、契約の有効期間を「5月1日から5月10日まで」と規定した場合、民法140条ただし書の「初日の起算点が午前0時から始めるときは初日を参入」するので、5月1日からが有効期間となります。
Ponit:
「本契約締結の日より」とあっても、その締結した日が入る時と入らない時があるので、注意しましょう!!
誤解を生じさせないためには、「5月1日から」のように、明確に日付を書いた方がいいです!!
【満了日】
期間のその末日の終了をもって満了します(民法141条)。
ただし、期間の末日が休日にあたりその日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日で満了します(民法142条)。
⑶ 「週・月・年」単位で定めた場合
【開始日】
日単位の時と全く同じです。
【期間の計算】
週・月・年の単位で表示されるときは、暦に従って計算します(民法143条1項)。
あくまでも暦に従うということがポイントです。
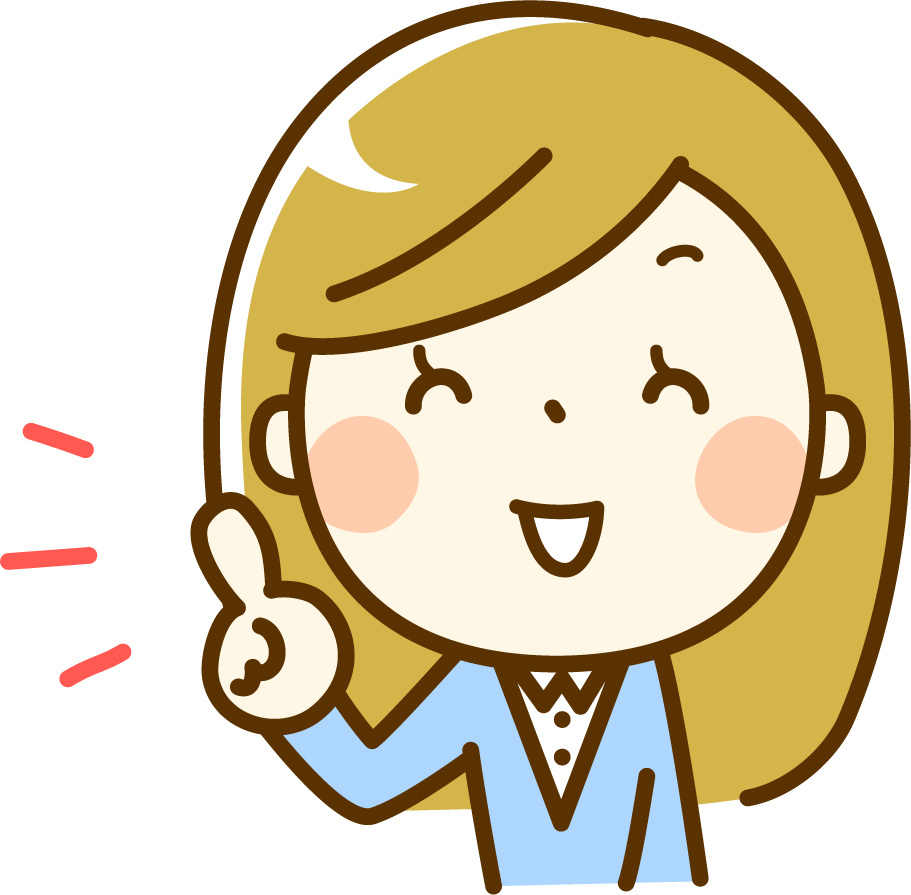
あくまでも「暦」に従うということがポイントなのですね!!
「5月から3カ月間」の有効期間とする条項では、7月末日が有効期間の終わりと理解できました。
そのため、月に30日あるときと31日あるとき、平年と閏年のときなどありますが、これらは一切区別しないことがポイントです。
ただ、週単位の場合には、1週間が7日間というのは明確なので、「7日単位」で計算します。
【満了日】
週、月または年の初めから期間を起算しないときは、その期間は最後の週・月・年においてその起算日に応当する日の前日に満了します(民法143条2項本文)。

15日から始める契約の時は、
その起算日(15日)の前日になるので、「14日」が満了日になるということですね。
ただし、月または年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します(民法143条2項ただし書)。

2月のように、30日や31日がない月で、30日や31日が末日に応当する場合は、2月の末日に期間が満了するということですね。
なお、期間の末日が休日(日曜や祝日)にあたり、その取引の日に取引をしない慣習がある場合に限り、翌日で満了します(民法142条)。

お正月に満了する契約になっている場合には、1月4日が満了日になるイメージを持てば良いですね。

2 自動更新条項
契約期間が満了すれば、原則として自動的に契約は終了となります。もっとも、企業間で締結される継続的契約においては、いずれかの当事者から意思表示なき限り自動的に契約が更新されていくという、いわゆる自動更新条項が規定されることが多いです。
【条項例】
本契約の有効期間は、令和4年5月1日から2年間とする。ただし、期間満了日の3カ月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示なき場合、同じ条件でさらに2年間更新されるものとする。
自動更新条項は、長期間にわたって契約関係を維持していきたい当事者にとっては、契約期間が満了するたびに契約更新の合意をしたり、再契約をしたりする手間が省けるというメリットがあるため、様々な契約類型において広く用いられています。
他方で、契約の更新を希望しない場合には、契約期間満了日の一定期間前までにその旨の意思表示をしなければなりませんので、更新の時期についてはしっかりとチェックをしておかなくてはなりません。

自動更新条項は、①更新を希望しない場合に、更新の時期をしっかりチェックすること、
②契約を締結するときに、当方にも更新拒絶権があるかをしっかりチェックすること、
覚えておかないといけませんね。
また、相手方当事者のみが更新拒絶権を有する形になっていたり、更新拒絶の意思表示をする期限が満了日の相当前に設定されていたりすることもありますので、この点は契約締結交渉段階で、契約更新拒絶権が不当に制約されていないか、この点もしっかりとチェックをしましょう。
【立場の違いに応じた修正の活用】
契約の立場によって、更新拒絶される場合には、それまでの準備(発注量の減少など)に時間を要することがあります。
そこで、立場の違いにより更新拒絶をする場合には、意思表示の期間に差異を設けたい場合も想定されます。
以下に、立場の違いを考慮した条項例をサンプルとして記載します。
【条項例】
本契約の有効期間は、令和4年5月1日から2年間とする。ただし、甲については期間満了日の6カ月前までに、又は乙については期間満了日の3カ月前までに、いずれの当事者からも相手方に対して書面による更新しない旨の通知がない場合には、同一条件で2年間更新され、以後も同様とする。
【関連記事】 継続的契約の中途解約・更新拒絶(期間満了)で注意すべき事は?
3 中途解約条項
契約は、有効に成立すれば、一方当事者から契約解除がなされたり、両当事者間で解約の合意が成立したりしない限り、契約期間が満了するまで有効に存続し、両当事者は契約内容に拘束されるのが原則です。
もっとも、長期間も拘束される契約を締結することに躊躇し、かえって安定的な契約関係を築くことが困難になってしまいます。
そこで、契約期間の途中でも、一方当事者からの意思表示のみで契約を中途解約できるとする、中途解約条項が規定されることが多いです。
【条項例】
甲又は乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して3カ月前までに書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。

いつでも自由に中途解約できるとすると、契約の拘束力が弱まりますね。
安易な中途解約を防止するために違約金などペナルティを課すこともあります。
中途解約を禁止することも考えられます(例:「甲及び乙は、本契約の有効期間中は、本契約を解約することはできない。」)。
また、違約金の支払義務を規定することで、事実上中途解約を制限することもありますね。
違約金は、下記の条項と異なり、定額にすることもあります。
【条項例】
甲又は乙は、本契約の有効期間であっても、相手方に対して3カ月前までに書面をもって通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、解約する場合は、解約日以降の本契約の残存期間の●●料相当額を違約金として相手方に支払わなければならない。
【関連】 中小零細企業に法務部を!経営を加速させる顧問弁護士の使い方とは?

 委託先コールセンター
委託先コールセンター


