被相続人が、特定の相続人だけに対して生前贈与や遺贈をした場合に、法定相続分どおりに遺産分割すると、その他の相続人にとっては、特定の相続人だけが遺産を多くもらっていることになり、不公平だと感じるかもしれません。
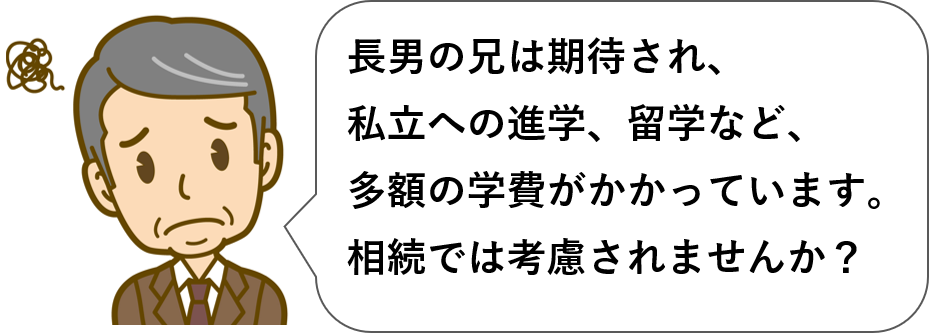
たとえば、相続人のうちの1人が、被相続人の生前に、多額の事業資金を援助してもらっていたり、結婚の際の持参金を渡されていたりすると、他の相続人は「1人だけ財産を多くもらっていてずるい」と思うでしょう。
このような場合、遺産分割において、「特別受益」を考慮して計算することが認められる可能性があります。
特別受益が認められれば、被相続人の生前に財産をもらっていた相続人の具体的相続分は、特別受益を考慮して計算します。
ただし、贈与が「遺産の前渡し」といえるほどでなければ、特別受益としては認められません。
「遺産の前渡し」といえるかどうかを判断するのは難しく、裁判例などの専門的な知識が必要となります。
この記事では、特別受益とは何か、特別受益の具体例、特別受益者の相続分の算定方法、立証に必要な資料や特別受益に関する裁判例を、弁護士がわかりやすく解説します。
【関連記事】あわせて読みたい
「相続」の発生~遺産分割手続の流れを弁護士がわかりやすく解説遺産相続のトラブルなど、
お気軽にご連絡ください。
全国対応
Zoom、Teams、
Google Meet等にて
相談料
1時間
11,000円
(税込)
不動産の相続は不動産相続の特設ページをご覧ください。
第1 特別受益とは
1 特別受益の定義
特別受益とは、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けたときの利益のことです(民法903条1項)。
たとえば、Aが亡くなり、相続人がAの子であるBとCだったとします。
Aの生前、BだけがAから相当な財産を生前贈与されていました。
本来、BとCは2分の1ずつ財産を相続することになりますが、Cは「BがAから生前贈与された分、自分が多く相続したい」と思うでしょう。
このように、被相続人から利益を受けた相続人も他の相続人と同じ相続分を取得するとすれば、他の相続人から見ると不公平になります。
そこで、民法上、共同相続人の公平を図るため、特別受益を相続分の前渡しとして、相続財産に持ち戻して相続分を計算することになっています。
2 特別受益にあたるかどうかの具体例
特別受益にあたるかどうかについては、一般的に、次のように考えられています(参照:東京家庭裁判所家事第5部『特別受益Q&A』)。
① 結婚の際の贈与
結婚の際の持参金や支度金は、一般的には特別受益にあたるとされています。
ただし、結納金や挙式費用は、特別受益にはあたりません。
② 居住用の不動産の贈与・その取得のための金銭の贈与(〇)
生計の基礎として役立つような贈与であり、特別受益にあたります。
③ 貸付金
「贈与」ではないため、特別受益にあたりません。
④ 小遣い・生活費
扶養の範囲内であるため、特別受益にあたりません。
生計の資本としての贈与とは、独立のための資金と考えられているため、遊興費の支払いのための贈与は、特別受益にあたりません。
⑤ 新築祝い・入学祝い・誕生祝いなどのお祝い
親としての通常の援助の範囲内でされたお祝いは、特別受益にはあたりません。
⑥ 学資(高等教育(大学等)を受けるための費用)(△)
被相続人の生前の経済状況や社会的地位を考えると、相続人を大学等に通わせることが親としての扶養の範囲内と判断される場合や、共同相続人全員が同程度の教育を受けている場合には、一般的に、特別受益にあたりません。
留学費用も、同様の場合には、一般的に、特別受益にはあたりません。
⑦ 生命保険金
原則として、特別受益にはあたりません。
例外的に、遺産の全体からみて、保険金を受け取る相続人と受け取らない相続人の間の不公平が、民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて、持戻しの対象となります。
⑧ 借金の肩代わり
被相続人が相続人の借金を肩代わりして支払った場合には、通常、その相続人に対して求償できるため、特別受益にはあたりません。
ただし、被相続人が求償権を放棄した場合で、肩代わりした借金の金額が遺産の前渡しといえるほど高額な場合には、特別受益にあたります。
⑨ 死亡退職金
労働協約や就業規則により、死亡退職金を受け取る遺族の生活保障という趣旨が明らかな場合は、特別受益にはあたりません。
他方で、個人企業の役員が死亡した場合など、死亡した者の長年の功績に報いるという色彩が強い場合には、特別受益にあたると考えられています。
⑩ 遺族給付
受給権者の生活保障を目的とした制度によって支出されたものであるので、特別受益にあたりません。
⑪ 被相続人の土地の無償使用(〇)
被相続人の土地の上に相続人が建物を建てて所有しているが、被相続人に対して土地の賃料を支払っていなかった場合、「使用借権」に相当する額の特別受益があるとされることが多いです。
ただし、その建物で被相続人と同居していた場合には、特別受益にあたらない可能性があります。
特別受益とされる場合でも、特別受益の金額は、使用借権相当額(更地価額の1割から3割まで)であり、賃料相当額(相当賃料額×使用年月数)ではありません。
⑫ 被相続人の建物の無償使用
被相続人の建物を無償で使用していた場合であっても、相続人が被相続人と同居していた場合には、特別受益にあたりません。
被相続人と同居していなかった場合でも、一般的には、特別受益にはあたらないとされており、家賃相当額が特別受益にあたるようなことはありません。
第2 特別受益者の相続分の算定方法
1 算定方法(算定手順)
特別受益者の相続分の算定方法を、分かりやすく説明します。
まず、「みなし相続財産」(≒特別受益が認定された場合の遺産総額)を計算します。
みなし相続財産は、相続財産に特別受益とされる生前贈与の額を加算した額です。
なお、特定の相続人が受けた遺贈については、相続財産に加算しません。
次に、みなし相続財産を各相続人で法定相続割合によって分けた金額が、「一応の相続分」となります。
そして、一応の相続分から特別受益分を控除した額が、特別受益者の具体的相続分となります。
このような特別受益者の相続分の算定方法を「持戻し計算」といいます。
【持戻し計算の計算式】
相続財産 + 特別受益(生前贈与) = みなし相続財産
みなし相続財産 ✕ 法定相続割合 = 一応の相続
一応の相続分 - 特別受益分 = 特別受益者の具体的相続分
なお、被相続人の意思表示により、特別受益者の持戻しを免除することができます(民法903条3項)。
この持戻し免除の意思表示は、通常、遺言によりされることが多いです。
2 具体的事例での算定
具体例で検討してみます。
想定事例
Aが亡くなり、相続人はAの妻であるB、Aの子であるCとDだったとします。
Aは、900万円の財産を残して亡くなりました。
Aは、生前、Cに居住用不動産の購入資金として100万円を贈与しました。
このケースにおいて、AがCに贈与した100万円が特別受益と認められれば、各相続人の具体的相続分は次のような計算になります。
1 遺産総額(みなし相続財産の算定)
特別受益を加算して、みなし相続財産を計算します。
| Aの遺産総額 :900万円 Cへの生前贈与:100万円 |
みなし相続財産
900万円 + 100万円 = 1,000万円
2 一応の相続分(法定相続分)の算定
相続人は、B(配偶者)、C(子)、D(子)の3名です。
法定相続分は以下のとおりです:
- B(配偶者):1/2
- CとD(子2人):1/2を2人で均等分割
それぞれの法定相続分は、次のようになります。
- Bの相続分:1,000万円 × 1/2 = 500万円
- Cの相続分:1,000万円 × 1/4 = 250万円
- Dの相続分:1,000万円 × 1/4 = 250万円
3 具体的相続分の確定(特別受益を差引く)
妻B:500万円
子C:250万円 - 100万円 = 150万円
子D:250万円
Cの特別受益(100万円)は、Cが既に受け取っているものとして考慮されます。
第3 立証に必要な資料
1 全般
受贈者が、特別受益を認めない場合には、特別受益を裏付ける証拠が必要となります。
特に、遺産分割調停や遺産分割審判においては、裁判所に特別受益があったことを認定してもらうために、客観的な証拠となる資料を提出しなければいけません。
例として、次のような資料が用いられます。
| 贈与の合意に関する資料 | 契約書などの合意書面、 被相続人作成の家計簿・日記・メール等、 預貯金通帳、 振込依頼書の控え、 |
| 生計の資本としての贈与であることを示す資料 | 被相続人の収入証明などの被相続人の資力に関する資料、 被相続人作成の日記、メール等、 被相続人から事情を聞いていた者の陳述書、 預貯金通帳、 振込依頼書の控え |
| 特別受益の金額を示す資料 | 不動産の固定資産評価証明書、 固定資産税納税通知書、 査定書 (贈与時から相続時までに貨幣価値が変動している場合) 消費者物価指数 |
具体的に、種類別に証拠となるものは何かを解説します。
2 現預金が贈与された場合
現預金が贈与されたことを立証するための資料には、被相続人や相続人の預金通帳、銀行の取引履歴、振込依頼書の控えなどがあります。
もし、現金で贈与された場合には、領収書があればいいですが、親族間の贈与で領収書を作っている場合はめったにないでしょう。
このような場合には、被相続人が預金通帳からまとまったお金を引き出しており、その引き出した直後に、受贈者が高額な物を買っていることを示す資料があれば、有力な証拠となり得ます。
3 不動産が贈与された場合
不動産を贈与された場合には、不動産の全部事項証明書(登記)を取得すれば、いつ・誰から誰に不動産の所有権が移ったかを確認できます。
不動産の購入資金を援助してもらった場合には、被相続人の通帳からまとまった金額が引き出されており、それが不動産売買契約書の締結時期と近接していれば、不動産の購入資金を援助してもらったと示すことができます。
4 車を贈与された場合
車が贈与された場合には、登録事項証明書を見れば、過去の名義変更がわかります。
車の購入資金を援助してもらった場合には、被相続人の通帳からまとまった金額が引き出されており、それが自動車売買契約書や車検証の時期と近接していれば、車の購入資金を援助してもらったと示すことができます。
5 学費を出してもらった場合
学費を振り込んだことがわかる預金通帳や振込依頼書の控えがあれば、学費を被相続人から出してもらったことがわかります。
また、実務上は、単に高等教育を受けたことだけをもって特別受益とは認められず、被相続人の資力・社会的地位・学歴等を勘案して特別受益かを判断します。
相続人全員が同程度の教育を受けている場合も、特別受益には該当しません。
そのため、被相続人の資力についての資料(預金通帳等)、被相続人と相続人全員の学歴についての資料(学位記等)もあると良いでしょう。
6 生活費を援助してもらった場合
被相続人の預金通帳や振込依頼書の控え、クレジットカードの利用明細等があれば、生活費を被相続人から援助してもらったことがわかります。
もっとも、単に被相続人から振込等をしてもらっただけでは特別受益とは認められず、背景事情も考慮されます。
たとえば、被相続人の資力と贈与額を比べて、贈与額が小さいときには、親族としての当然の援助の範囲とされる可能性もあります。
このような場合には、被相続人の資力についての資料(預金通帳等)があると良いでしょう。
7 借金を肩代わりしてもらった場合
被相続人の預金通帳や振込依頼書の控えがあれば、借金を肩代わりして返済したことがわかります。
また、借入先の金融機関や消費者金融が発行した取引明細書や完済証明書があれば、借金をいつ返済したか・いくら返済したかがわかるでしょう。
8 事業資金を援助してもらった場合
事業資金を援助してもらった場合は、被相続人の支出と開業時期が近接していることを示すと良いでしょう。
たとえば、被相続人の預金通帳や振込依頼書の控え等から、被相続人がまとまった金額を引き出している時期と、開業時期が近接していれば、事業資金を援助してもらったとわかります。
他にも、被相続人とのメールのやりとりや、被相続人の日記、メモ等で、事業資金を援助したことがわかるやりとりがあれば有力な証拠となります。
遺産相続のトラブルなど、
お気軽にご連絡ください。
全国対応
Zoom、Teams、
Google Meet等にて
相談料
1時間
11,000円
(税込)
不動産の相続は不動産相続の特設ページをご覧ください。
第4 裁判所の判断(審判)事例 ~ 特別受益はどのような判断をされるのか?
1 東京家審平成21年1月30日(家月62巻9号62頁)
被相続人は、子である相続人に対して、生前、2年余りの間に毎月2万円から25万円を送金していました。この送金が特別受益にあたるのではないかが争点となりました。
裁判所は、遺産総額(約2億6700万円)や被相続人の収入状況からすると、一月に10万円を超える送金は、生計資本としての贈与と認め、持戻しの対象としました。
他方、10万円に満たない送金については、親族間の扶養的金銭援助にとどまり、生計資本としての贈与とは認められないと判断しました。
2 大阪高決平成19年12月6日(家月60巻9号89頁)
被相続人は、小学校卒業後、農業に従事し、村会議員や農協専務理事等を務めていました。
相続人らは、大正後期から昭和10年までに出生した子5人でした。
子5人のうち、女性4人は、高等女学校や師範学校等を卒業して、教員等になった後に結婚しました。
他方、長男は、大学附属中学から大学卒業までの10年間を下宿して過ごした後、教員になりました。
この長男の学費と下宿費が、他の子の教育に関する出費と比べて歴然たる差があり、特別受益にあたるのではないかが争点となりました。
裁判所は、「被相続人の子供らが、大学や師範学校等、当時としては高等教育と評価できる教育を受けていく中で、子供の個人差その他の事情により、公立・私立等が分かれ、その費用に差が生じることがあるとしても、通常、親の子に対する扶養の一内容として支出されるもので、遺産の先渡しとしての趣旨を含まないと認識するのが一般」であると判断しました。
また、「仮に特別受益と評価しうるとしても、特段の事情のない限り、被相続人の持戻免除の意思が推定されるものというべき」としました。
本件では、長男の学費と下宿費は、特別受益にあたらないと判断されました。
3 名古屋高等裁判所令和元年5月17日(判時2445号35頁)
被相続人Aが亡くなり、妻とその子であるXとY、そして前妻との間の子1人が相続人となりました。
Xは、大学、大学院に進学し、その後10年間フランス、アメリカおよびイギリスへ海外留学をしていました。
海外留学費用は、被相続人Aが負担していました。
Xの学費や海外留学費用が、特別受益にあたるのではないかが争点となりました。
裁判所は、「学費、留学費用等の教育費については、被相続人の生前の資産状況、社会的地位に照らし、被相続人の子である相続人に高等教育を受けさせることが扶養の一部であると認められる場合には、特別受益に当たらないと解するのが相当である」としました。
そして、本件では、
- A一家は教育水準が高く、その能力に応じて高度の教育を受けることが特別なことではなかったこと
- Xが学者、通訳者または翻訳者として成長するために相当な時間と費用を費やすことをAが許容していたこと
- Xが自発的にAに相当額を返還していると認められること
- AがXに対して援助した費用の清算や返済を求めるなどした形跡がないこと
- Aは、生前、経済的に余裕があり、YやYの妻に対しても、高額な時計を譲り渡したり、宝飾品や金銭を贈与したりしていたこと
- Yも一橋大学に進学し、在学期間中に短期留学していること
- Aが支出した大学院の学費や留学費用の額、Aの遺産の規模等
に照らせば、Xの大学院の学費、留学費用は、Xの特別受益に該当するものではなく、仮に特別受益に該当するとしても、Aの明示または黙示の持戻免除の意思表示があったものと認めるのが相当と判断しました。
4 最二小決平成16年10月29日(民集58巻7号1979頁)
被相続人が、自らを被保険者とし、保険金受取人を共同相続人のうちの1人として締結していた養老保険契約2口に基づく死亡保険金合計574万0289円が特別受益として持戻しの対象となるかが争点となりました。
裁判所は、「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である」としつつ、「もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」という判断を示しました。
そして、この特段の事情の有無については、「保険金の額、この額に対する遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」として、考慮要素を例示しました。
本件では、特段の事情があるとはいえず、特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものではないと判断しました。
5 福島家白河支審昭和55年5月24日(家月33巻4号75頁)
被相続人である父が亡くなり、相続人は被相続人の子4人でした。
被相続人は、生前、相続人の1人であるAの配偶者B(夫)に対して、農地を贈与していました。
この相続人の1人の配偶者への農地の贈与が特別受益にあたるかどうかが争点となりました。
裁判所は、「本件贈与は、相続人であるAに対してではなく、その夫であるBに対してなされているのであるから、形式的に見る限り特別受益にはあたらないことになる。
しかし、通常配偶者の一方に贈与がなされれば、他の配偶者もこれにより多かれ少なかれ利益を受けるのであり、場合によっては、直接の贈与を受けたのと異ならないこともありうる。
遺産分割にあたっては、当事者の実質的な公平を図ることが重要であることは言うまでもないところ、右のような場合、形式的に贈与の当事者でないという理由で、相続人のうちある者が受けている利益を無視して遺産の分割を行うことは、相続人間の実質的な公平を害することになる」という判断を示しました。
そして、「贈与の経緯、贈与された物の価値、性質これにより相続人の受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められる場合には、たとえ相続人の配偶者に対してなされた贈与であってもこれを相続人の特別受益とみて、遺産の分割をすべきである」として、考慮要素を例示しました。
本件では、
- 本件贈与はA夫婦が分家をする際に、その生計の資本としてAの父親である被相続人からなされたものであること
- とくに贈与された土地のうち大部分を占める農地についてみると、これを利用するのは農業に従事しているAであること
- 本件贈与は被相続人の農業を手伝ってくれた謝礼の趣旨も含まれていると認められるが、農業を手伝ったのはAであること
などの事情からすると、被相続人が贈与した趣旨はAに利益を与えることに主眼があったと判断しました。
登記簿上Bの名義にしたのは、Aが述べているように、夫を立てた方がよいとの配慮からそのようにしたのではないかと推測しました。
結果的に、裁判所は、本件贈与は直接Aになされたのと実質的に異ならないし、その評価も、遺産の総額が2147万3000円であるのに対し、贈与財産の額は1355万1400円であり、両者の総計額(3502万4400円)の38パーセントにもなることを考慮すると、本件贈与によりAの受ける利益を無視して遺産分割をすることは、相続人間の公平に反するというべきであり、本件贈与はAに対する特別受益にあたると判断しました。
第5 まとめ
相続人のうちの1人が、被相続人から、生前贈与や遺贈を受けていた場合、法定相続分どおりに遺産分割すると、他の相続人は不公平に感じます。
この贈与が、遺贈や、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」といえる場合には、特別受益にあたる可能性があります。
特別受益にあたるのであれば、特別受益は持戻し計算の対象となり、具体的相続分を決める際に特別受益を考慮して計算することになり、相続人間の公平を図ることができます。
もっとも、特別受益は「遺産の前渡し」と評価できるかがポイントとなり、その判断には裁判例やこれまでの経験などの専門的な知見が必要となります。
また、特別受益を受贈者が認めない限りは、客観的な証拠がないと認められづらく、どのような証拠が必要か、専門家でないと判断が難しいです。
仮に、特別受益の主張が認められるとしても、いったい自分にいくらの相続分が認められるのかという計算も複雑です。
当該贈与が特別受益にあたるのか、特別受益の主張のためにどのような証拠が必要なのか、特別受益の主張が認められた場合の具体的な相続分はいくらなのか等、法的知識を用いた対応が必要不可欠です。
相続人の中に被相続人から贈与を受けた者がいて、法定相続分どおりの遺産分割では納得がいかないという方は、まずは相続に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
遺産相続のトラブルなど、
お気軽にご連絡ください。
全国対応
Zoom、Teams、
Google Meet等にて
相談料
1時間
11,000円
(税込)
不動産の相続は不動産相続の特設ページをご覧ください。

 委託先コールセンター
委託先コールセンター



