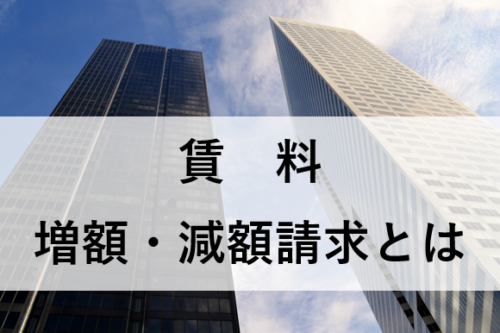休業(補償)等給付は、業務災害・通勤災害によってケガや病気を負い、療養のため働くことができず、賃金が得られていない場合、その4日目から1年6ヶ月を限度に次の給付を受けることができます。
| 種類 | 内容 |
| 休業補償給付 | 業務災害によるケガや病気などの治療で労働することができず、賃金を受けられない場合に行われる給付 |
| 休業給付 | 通勤災害によるケガや病気などの治療で労働することができず、賃金を受けられない場合に行われる給付 |
休業補償給付と休業給付では、いずれも給付される内容はほぼ同じです。
業務災害に対する給付については、使用者が負っている補償責任を担保するとの考え方から、「補償」という文字が入っています。
一方、通勤災害に対する給付は、使用者に補償責任はないため、「補償」という文字が入っていません。
1 給付条件と内容
休業補償等給付を受けるためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。
- 業務上の事由または通勤によるケガや病気による療養が必要
- 働くことができない
- 賃金を得ていない
上記の要件を満たした場合、4日目から休業(補償)等給付と休業特別支給金の支給を受けることができます。
単一事業労働者(一つの事業場のみに使用されている労働者)の場合
- 休業補償給付、休業給付 =(給付基礎日額の60%) × 休業日数
- 休業特別支給金 =(給付基礎日額の20%) × 休業日数
複数事業労働者(事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者)の場合
- 休業(補償)等給付=(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)×休業日数
- 休業特別支給金=(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)×休業日数
一部を休業した場合
労働者が、通院などで所定労働時間のうち一部を休業した場合には、給付基礎日額から実際に働いた部分に対して支払われる賃金額を控除した額を算出し、その60%が支給されます。
待機期間の設定
休業補償給付では、待機期間が設定されています。
休業した初日から3日目までで、この間は休業補償等給付を受けることはできません。
ただし、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(平均賃金の約60%)を行います。
2 給付基礎日額とは
給付基礎日額とは、業務上または通勤によるケガや病気などの原因となった事故が発生した日、または医師の診断によって罹患が確定した日の直前3か月間に、被災労働者に対して支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を、その期間の暦日数で割った賃金額(1日当たり)を指します。
具体例は次のとおりです。
例)月額30万円の賃金を受ける者が、3月31日に労災事故に遭った(事故発生)場合
- (30万円×3ヶ月)÷90日間 = 1万円
なお、複数事業労働者の給付基礎日額については、原則、複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。
被災労働者の一部負担金
通勤災害によって療養給付を受ける場合、被災労働者の一部負担金があります。
その額は200円で、初回の休業給付から一部負担金としてこの金額が減額されます(日雇特例被保険者については100円)。
なお、業務災害によって療養給付を受ける場合は、上記のような一部負担金はありません。
3 請求の手続き
休業補償等給付を請求する手続きについて、一般労働者の例を挙げて順序を説明します。
| 順序 | 項目 | 内容 |
| 1 | 請求書の作成 | 請求書の書式は厚生労働省が示しており、ダウンロードが可能。 記入例を参考にして作成を進めましょう。 🔗書式(厚労省サイト) |
| 2 | 事業主の証明 | 休業補償等給付の請求書には、事業主の証明が必要な箇所があるため、勤務先に証明してくれるよう協力を依頼する。 事業主からの協力が得られにくい場合は、証明が得られない理由を書いた書類を添付して3へ。 |
| 3 | 請求書を労働基準監督署へ送る | 管轄の労働基準監督署に請求書を送付。 労働基準監督署の所在地は、厚労省のサイトから調べることができます。 🔗「全国労働基準監督署の所在案内」(厚労省サイト) |
| 4 | 労働基準監督署が調査を行う | 労働基準監督署が請求書の内容を確認し、記載内容に誤りが無いかチェックを行うとともに、必要に応じて被災労働者や事業所に対して事実確認や調査を実施する。 |
| 5 | 支給・不支給の決定 | 労働基準監督署が支給・不支給を決定し、被災労働者に対して通知を行う。 |
| 6 | 支払い | 被災労働者に対して休業補償等給付が支払われる。 |
なお、休業が長期間になる場合は、1か月ごとの請求が一般的です。
休業特別支給金の申請に関しては休業等給付の請求と同時に行うことが原則となっています(様式も同じ)。
請求権の消滅事項
休業補償等給付は、療養のために労働することができず、賃金を受けられない日ごとに請求権が発生しますが、その翌日から2年が経過すると、時効により請求権が消滅してしまいます。
この場合、被災労働者は休業補償給付を受けられなくなるので充分に注意しましょう。
4 注意点
以下、休業補償給付に関する注意点を記します。
休業期間が4日間未満の場合
休業期間が4日間未満の場合は、休業補償給付の支給対象となりません。
よって、給付を受けることができません。
不支給の決定に不服がある場合
労働基準監督署による不支給の決定や、その内容や理由に不服がある場合は、管轄の労働局に審査請求を行うことができます。
この審査請求とは、行政が行った決定・裁定に納得がいかない、不服がある場合にその申し立てをする行為を指します。
もし万が一、休業補償等給付の不支給の決定を受け、その内容に納得がいかなければ、弁護士事務所などに相談したうえで審査請求を検討しましょう。
5 まとめ
この記事では休業(補償)給付の内容と請求手続きの方法について解説しました。
休業補償等給付は、業務または通勤中のケガや病気によって、仕事ができない方を補償してくれる制度です。
休業補償等給付に不明なことがあれば、管轄の労働基準監督署や労働法規に強い弁護士事務所へ相談してみることをお勧めします。
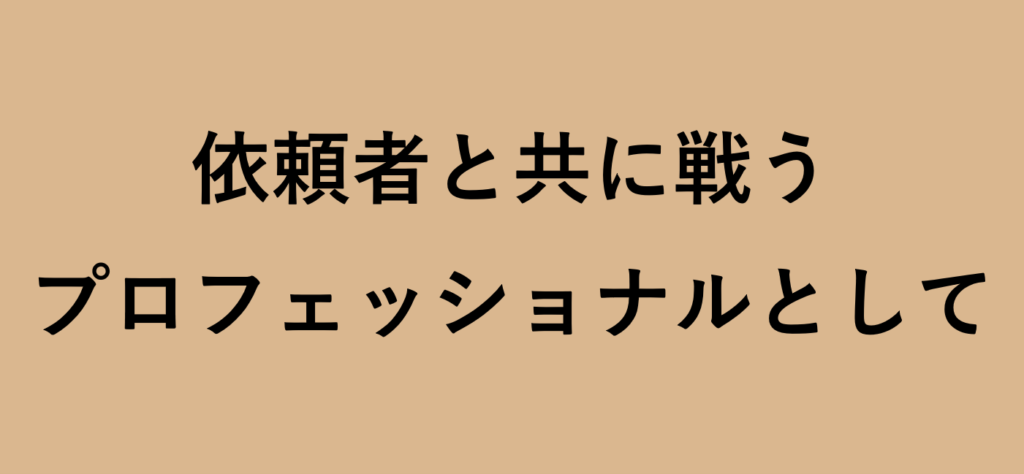
労災被害や過労死は、適切な治療を最後まで受けたかどうか、必要な証拠を集められたかどうか、によって結果も異なってきます。
労災被害者の方が適正な権利救済を求め続ける限り、私たちは専門家として共に戦います。
労災無料診断フォーム
お問い合わせ
来所相談だけでなく、お電話による相談や、Zoom・Google Meetによるオンライン相談も対応しておりますので、全国対応しております。
法律相談お申込みフォーム、LINE、お電話にてご連絡ください。
相談時に必要なもの
事前に以下のものをご準備いただくと、ご相談がスムーズに進みます。
- 相談内容の要点をまとめていたメモ
- ご相談に関する資料や書類
ご相談(初回30分:相談料無料)
法律上の問題点や採り得る手段などを専門家の見地よりお伝えします。
問題解決の見通し、今後の方針、解決までにかかる時間、弁護士費用等をご説明いたします。
※ご相談でお悩みが解決した場合は、ここで終了となります。
ご依頼
当事務所にご依頼いただく場合には、委任契約の内容をご確認いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
問題解決へ
事件解決に向けて、必要な手続(和解交渉、調停、裁判)を進めていきます。
示談、調停、和解、判決などにより事件が解決に至れば終了となります。
終了
委任契約書の内容にしたがって、弁護士費用をお支払いいただきます。
お預かりした資料等はお返しいたします。

 委託先コールセンター
委託先コールセンター